グラブ豆知識👏として今回は当て革(硬式グラブ)について考えてみたいと思います。
グラブの内部には当て革がある
グラブの表と裏の間には、今のグラブはほとんど当て革が入っています。
当て革は捕球面側あるいは裏革に糊で接着されています。
メーカーによっては本体に縫い込んでいたり、紐が通るようになっていたりします。
メーカーによって当て革のサイズや付け方はバラバラです。

当て革を見ただけでどこ製のグラブなのか、スポーツ店で修理をしている方はわかるかもしれません。それだけ特徴がでるところだと思います。
グラブに当て革を入れる理由
なぜ今のグラブは当て革をいれるのか?これについては推測になります。
一言で言うと軽量化・柔軟性が求められる中で、相反する耐久性も求められるから ですね。
軽くしようと思えば革が薄くなりますし、柔らかい材料を使えば捕球面にパンと張りがでません。
そこを補うのが当て革でしょう。

捕球面が頼りない感じだと嫌だという人も多いと思います。そういった理由からも捕球面を張らせる(良い悪いは別として)必要があります。
グラブの当て革はほぼ必ず剥がれる
どんなに高価なグラブでも当て革はほぼ剥がれるようです。特に捕球面側の革に接着してある当て革は間違いなくはがれてきます。
それ自体は悪い事ではありませんし、仕方のないことです。

このように綺麗にはがれると、とたんに柔らかく感じるようになります。隙間が出来るからですね。
グリスが無くなった気がしたら当て革が剥がれているかも
よく、「柔らかくなったのでグリスを入れて」と持ってこられますが、大半当て革も剥がれています。
なので「当て革剥がれたみたいなので付けてください。一緒にグリスもお願いします」と持ってこられたらかっこいいですね(笑)
良いグラブでしたら再接着+グリス補充で捕球面の張りがよみがえります。
グラブの当て革を再接着
ゴムのりでグラブの当て革を再接着して、グリスを補充します。
いつもはG17とかを使用してますが、ボンドのように硬化せず接着できるゴムのりがよろしいかと思います。
硬式向け加工も当て革をします
当店では「加工する価値のあるグラブ」に限り、硬式向け加工を行っております。
そこでも当て革をします。基本は平裏側につけます。
これによって重くなりますが、捕球面の張りはかなりでます。
ボールを受けるときに柔らかい紙で受けるか、ピンと張った皺のない紙で受けるか、これで衝撃は違ってきます。
重くなるのはデメリットですが、安全性という点でも必要になるかと思います。
まとめ – 当て革にグラブの違いがでる
グラブの当て革の作り方でメーカーによりかなりの違いが出ます。しかし、基本的には1年もすれば剥がれてきますのでメンテナンスが必要です。ですから、メンテナンスをしてくれる店で購入、または対応してくれる店の目星をつけておくと宜しいかと思います。
当店でも承っております。何かありましたらお問い合わせください。
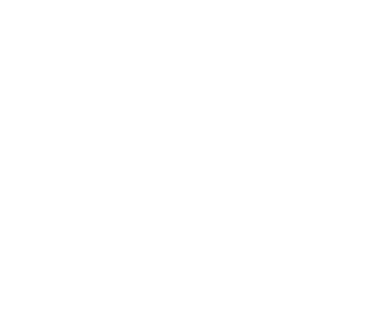
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2f0b2227.43848a82.2f0b2228.67397284/?me_id=1303115&item_id=10007727&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flc-palette%2Fcabinet%2Fproduct26%2Fe83013.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

